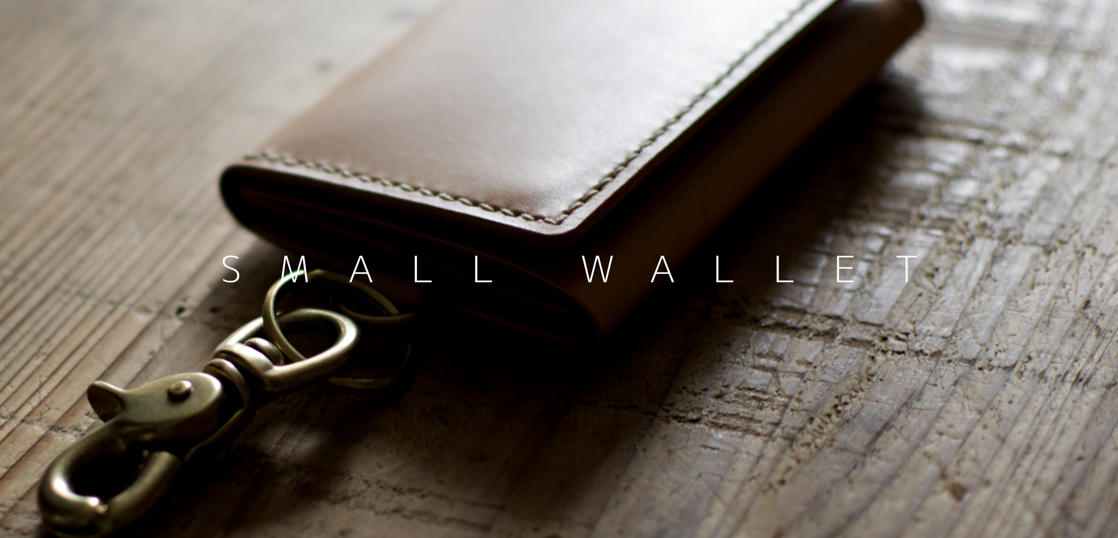ナチュラルで素朴なデザインの石鹸がよく雑貨屋さんなどに並んでいますが、それを自宅でも簡単に作ることが出来るとしたらよくないですか。
手作りだと自分の好きなハーブや精油を自由に練り込むことができて楽しいですし場合によっては経済的です。
そこで、石鹸の作り方を調べてみることにした。
まず最初に調べたのは本格的な石鹸を作る方法。
雑貨屋さんなどにあるような、あの角々としていていかにも手作りという感じの無骨なデザインの石鹸が自宅で作れるかもしれないと考えると、ちょっとうれしくなってくる。
でも、調べが進むにつれて徐々にテンションが下がってしまうことに…。どうやら材料として苛性ソーダという危険な薬品が必要だということらしくそこでちょっとくじけてしまう。

次に調べたのは『手作り専用の石鹸素地』という市販の材料を用いて作る方法。これだと安全で簡単。
そしてさらに調べてみると『普通の石鹸』を細かく削ってそれを素にして作るという方法も…。
ただその場合、作るというよりもリメイクするという感じかもしれませんが…。
ともあれ、後者の作り方の場合だと近所にあるスーパー・ホームセンター・ドラックストアなどで手軽に材料を購入することができます。
つまり、自宅でいつも使用している『普通の石鹸』ですぐに作れるということでもある。しかも1個からでも…。
ということで、自宅にあったストックを利用してオリジナルの石鹸を作ってみることにした。
なお普通の石鹸とはいっても、無香料・無着色の石鹸素地100%で出来たタイプのモノを使用します。

なおその前に『手作り専用の石鹸素地』で作るパターンも気になったので市販の袋入り素地を購入してとりあえず作ってみることにした。
『普通の石鹸』を細かく削ったものを材料とするパターンとの差も知りたかったし…。
まず当然ですが、この『手作り専用の石鹸素地』はとても気軽に作れます。
結果としては、すごく練り易くて最終的にはしっかりとしたものに仕上げることが出来ました。
また、削る道具なども使用しないため楽ですし安全です。なので細かく削る作業が面倒で嫌だという方にはおすすめかもしれません。
自分好みの精油を入れてハーブなどの香りを付けることも可能ですし…。
ただ、下記で行った『普通の石鹸』を細かく削ったものを材料とする方法でも、そこそこ同じようなものは作れました。
■普通の石鹸をリメイクしてオリジナルを作る。
ここでは、1個(100g程)からでも手軽に購入することができる『普通の石鹸』で作ることにします。
なお、水分量や作り方は、市販の『手作り専用の石鹸素地』の場合とは多少変えました。

【無香料で無着色の石鹸】… 1個(100g程)
[石鹸素地100%・無添加]というような品質表示がパッケージのどこかに書いてあるはずですのでそのタイプを選びます。
【水分】… お湯または水を40g程(40cc)
ハーブの香りを付けたい場合…
■精油(エッセンシャルオイル)を使うのであれば、下記の材料を追加する。
【ハーブの精油】3~5滴程
■ハーブティーを使うのであれば、上記の【水分】のところを下記に変える。
【ハーブティー】40g程
※色々と試してみましたが、加える水分はすごく正確に量る必要はないという感じです。
100gの素地に対して、加える水分を20g・30g・40g・50gとで作ってみましたが、いずれもそれなりに出来ました。
この加える水分量は、石鹸の種類・乾燥状態(日にちの経っているモノほど乾燥が進んでいる)によっても変わってきます。
なお、加える水分量が少ないと成形中にモロモロと割れ易くなります。
逆に、加える水分量が多いほどネットリとなり、道具などにこびり付き易くなって扱うのが厄介にはなります。そして完成した後の乾燥も遅くなります。
■使用する道具
【削り器】 おろし金(大根おろし器)や、チーズグレーター(チーズおろし器/削り器)
【ポリ袋】 なるべく厚めのものを使用したほうが色々と作業はし易いです。
【手袋】 炊事用のビニール手袋やゴム手袋
【型枠】 お菓子の型や、適当な形の箱
【ラップ】 型枠から取り出し易くするためのもの
※型枠は、手で成形する場合は無くてもよいです。
■作り方

1.まず、おろし金やチーズグレーターなどを使って石鹸を細かく削ります。
今回はおろし金で削りました。
削る前は『けっこう力が必要なんだろうな…。』と思っていたのですが、以外と楽で、チーズや大根を削る時と同じぐらいの力で大丈夫でした。
なおこの削る作業をする時には、器具で怪我をしないように十分に注意が必要です。
そして、削った後に周りを見てみると結構粉が飛び散っていたので、下に置くボウルやトレーは大き目のものが良いかと思います。
また、おろし金には石鹸がこびり付きはしますが、元々は洗剤のようなものなので水で流しながらブラシなどで軽く撫でると簡単に落とせます。
※市販の『手作り専用の石鹸素地』を使う場合、この作業は必要がないので楽ですし安全です。

2.ポリ袋の中に細かく削った素地100gを入れ、そこに、水分40g程を数回に分けて加えながら均一に混ぜていきます。
ハーブの香りを付けたい場合は…
●お湯40g程(水でもOK)と一緒にハーブの精油3~5滴程を加えます。
●もしくは、ハーブティーを濃い目に作って、それをお湯の代わりに40g程加えます。この場合、精油は加えても加えなくてもお好みで。そこはハーブティーの香り次第かな…。
※ハーブや精油には色々な効果はありますが、アレルギー体質や敏感肌の人はご使用をお控えになった方がいい場合もあります。
ちなみに、精油(エッセンシャルオイル)を多めに加えると、芳香剤(石鹸ではなく雑貨)としても使えます。またその場合、ドライハーブやドライフルーツなどの固形のものを加えて、見た目を楽しむのもいいですね…。
なお、この工程で加える水分としては基本的にお湯か水になりますが、その代わりとしてコーヒーや紅茶などの色の濃い液体を加えると色の濃い渋めな雰囲気の石鹸が作れます。ただその場合、ハーブを入れるか入れないかは液体の時点でちょっとだけ混ぜて香りのチェックをしてみたほうがいいかも。相性の良くない香もあるとは思うので…。

3.ポリ袋の上から中の素地を練ります。
加えた水分や精油などが均一に混ざるように練っていきます。
このとき、加える水分が無色 もしくは薄い色の場合はそのまま固めても気にはなりませんが、
濃い色の液体(例えば濃い色の紅茶など)を加えた場合は素地の白い粒粒は多少目立ちます。
もしそれが嫌な場合は、ある程度混ぜた後に、数時間そのまま(乾燥しないように密封した状態で)放置しておくと粒粒の素地がふやけて比較的潰れ易くなってくれます。
おまけに、このあとの成形する際には、多少割れ難くなってもくれます。
なお潰す際には、ポリ袋を平たくしてテーブル等の上に置き、指で押しながら潰すとやり易いです。
その時、袋の端部分辺りで潰すと袋が破裂しやすいので、真ん中辺りで潰します。
ただ、水分を多めに加えた場合には、中身が袋にベッタリとこびり付いて取り出し難くはなってしまいますが…。

また、ポリ袋ではやり難いという場合は、中身をボウルなどに移し、炊事用のビニール手袋やゴム手袋をはめた手で練り混ぜても良いです。

4.好きな形に手で成形するか、または、好きな形の型枠に入れて成形します。
ポリ袋の中から素地を取り出し、両手で挟んでコロコロと転がしながら団子状にしてゆきます。
そのあと、手で好きな形に成形するか、もしくは型に押し込んで成形します。
それらの作業をする際には、手にビニール手袋などをするか、素地をラップで覆うかします。
なお、手で成形したものは多少デコボコとした形になってしまいますが、それはそれでハンドメイドらしくて味があります。
また、成形するときは100g(1個分)全部を丸々1個に固めてしまわずに、数個に分けて小さいサイズのモノをいくつか作るのもかわいいですし、好きな形の型枠や、ケーキやクッキーの型などに入れて成形するのも楽しいですよ。
型枠として使用するものは、適当な大きさのしっかりとした箱ならなんでもよいと思います。
なお、型枠の材質によっては型枠に素地がこびり付いてとれなくなる場合もありますので、その場合は素地を入れる前に型枠の中にラップを敷きます。

5.成形後は、直射日光を避けて重ならないようにして乾燥させます。
加えた水分の量や、完成したものの厚さによって乾燥の日数は異なります。
素地100gに対して水分量が40gほどの場合、厚さ15mmくらいに成形すると大体2週間以上はかかると思います。とうぜん、加える水分の量が多いほど乾燥日数は長くなります。
なお、日光にあてると酸化しやすくなるので、乾燥させるときは日陰で風通しの良い場所を選び、さらにはカビないようにするために網やザルの上にのせておきます。
もし網やザルがなければ、割り箸などを2本並べてその上に石鹸が浮いたようにして置いておくというのもいいかも。
そして、複数個作った場合は乾燥中にお互いが重ならないように。
保存方法
日光や光の当たらない冷暗所で保存します。
使用期限
作ったものはなるべく早く使いきるようにします。遅くても半年以内には使いきるようにしたほうが良いでしょう。
但し、半年以内でも、匂いが変わった・すごく色が変わった・ベタベタしてきた・その他あきらかに何かが変わった(酸化や腐敗が進んだ)なと感じたら処分の対象です。
とにかく、使用する石鹸・中に加えるもの・作り方・保存状況などによってもそこらへんは変わるはずです…。まあ、一度にたくさん作り過ぎなければよいだけですが…。

以上の作り方が、ハンドメイドで作る石鹸の中では最も手軽で安全な作り方だと思います。
なお、今回ハンドメイドで作ったモノは、個人用として自分で使用するものです。
また、使用前には必ずパッチテストは実施。
自分の場合はいきなり顔や身体には使用せずに、まずは手洗いで試しています。
加えたものが肌に合わないとまずいですからね。
とにかく、材料となる石鹸や精油の説明書は必ず読むこと。
ハーブや精油や何かを加える前には、身体への影響や効能については必ず調べること。
もし、なにかのアレルギー反応や異常が起きたら、使用をやめて必ずお医者さんには見せること。
などが大事です。
なお、今回は簡単な作り方を紹介しましたが、苛性ソーダを使用していないのに「なめらか」に作るというような、今回とは違ったハンドメイドの方法もあります。
下記のページでは、それらも紹介しますので、興味のあるかたはどうぞ。
↓こちら
苛性ソーダを使わない手作り石鹸の作り方と その材料